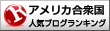アメリカで妊娠出産 | 初診の流れ、必要な準備、出生前診断について【体験談】in アトランタ

アメリカで妊娠、出産を経験する際、日本とは異なるので不安になることも多いと思います。今回は、初診の流れや、初診に行く前に準備しておくと良いことについてまとめました。「妊娠発覚~病院探し」の情報は、下記の別の記事で詳しく紹介しています。
大まかな出産までの流れ

まず、妊娠発覚から出産に至るまでの大まかな流れを紹介します。日本語では、妊娠初期、中期、後期という言葉を使いますが、英語では呼び方が異なります。時期も日本とアメリカでは微妙にずれているようです。
【第1期(0週~12週)】
日本語での「妊娠初期(0週~15週)」は、英語で「First Trimester」
・妊娠発覚、妊娠チェック
・産婦人科を探して、初診の予約をとる
・初診(妊娠8週目以降)
・定期健診(およそ1か月に1回)
【第2期(13週~26週)】
日本語での「妊娠中期(安定期、16~27週)」は、英語で「Second Trimester」
・定期健診(およそ1か月に1回)
【第3期(27週~40週)】
日本語の「妊娠後期(28週~40週)」は、英語で「Third Trimester」
・隔週健診(29週以降は2週間ごと)
・毎週検診(35週以降は週に1回)
高齢出産(35歳以上)や、双子などの高リスク出産の場合、検診のスケジュールは異なります。
初診の流れ

ここからは、筆者が実際に体験した初診の様子を紹介します。ドクターや病院、また加入している保険によって、流れや内容は異なると思いますので、ひとつの参考例としてご覧ください。
初診の予約
妊娠が発覚した後、産婦人科を探し始めました。毎年、健康診断を受けていた日系のクリニックに紹介されたドクターで、多くの友人が出産を経験しているドクターが、保険適用範囲内だったので、そこに通うことにしました。(ちなみに、アトランタ周辺に住む筆者が通っていたのは、Northside Hospital AtlantaのOB/GYNです。Northside Hospitalは、アトランタ周辺で複数の病院を運営しています。)
まずは電話で初診の予約をとりました。最終生理開始日から、妊娠8週目以降を計算して、その頃に予約をとることになります。なので、予約をとる前に、以下の情報を準備しておくとスムーズです。
・個人情報(名前、電話番号など)
・最終生理開始日
・保険の種類
(ちなみに、筆者が通っていた場所は、オンラインサイトも充実していて、ネットで予約のリクエストを送ることもできました。参考:Women's Health Associates Group Atlanta)
初診当日
初診当日の流れを紹介します。当日は旦那さんと一緒に病院へ行きました。日本では産婦人科の待合室には女性ばかりが居るイメージですが、アメリカでは夫婦で受診することも普通なので、その日も何組もの夫婦が居ました。
・病院到着
・産婦人科のある場所へ
・受付(身分証明書や保険証を準備しておく)
・問診表や同意書の記入
・看護師による、身長&体重測定、尿検査
・看護師による問診、血圧測定
・ドクターの診察、経腟エコーで胎児の確認
・ドクターと質疑応答、今後の説明(出生前診断について)など
・血液検査
・次回の検診の予約
初めてその病院に行く場合、駐車場でスムーズに駐車できるか、そこから産婦人科のある部屋までスムーズに移動できるかなど、混み具合や距離感が把握できていないと予想以上に時間がかかる可能性があるので、早めに移動しましょう。
エコー検査について

日本では、毎回の診察で、エコー検査(超音波検査)があるようですが、アメリカでは全体を通して約3回のように、日本に比べてエコーによる検診の回数が少ないです。通常の検診では心音のみの確認です。また、エコー検査は別の専門医が行う場合があり、病棟や病院の場所が異なる場合があります。エコーの回数は、妊婦の状況や選択する検査の種類などによって異なります。また保険によって適用範囲も異なるので、人によってエコーを受ける回数は変わります。
初診の経腟エコーで胎児の様子を確認する頃(妊娠8週後)は、胎児のサイズがミニトマトくらいと言われます。後述する出生前検査のひとつ「第1期スクリーニング(1st trimester screening)」を受けない場合、おそらく、次に胎児の様子をエコーで見られるのは、妊娠20週頃に胎児の身体的欠陥を確認する「第2期スクリーニング(2nd trimester screening)」の時です。その頃には、見た目で性別が分かり、胎動も感じられ、ピーマンくらいのサイズと言われます。初診の後に胎児を見られるまで、かなり時間が空く場合があるので、ぜひ初診のエコーをしっかり見て、写真ももらっておくと良いでしょう。
準備すること

ここからは、初診でどんなことがあるのか更に詳しく説明した上で、それに向けて準備しておいた方が良いことを紹介します。
問診表と同意書
個人的に初診で一番疲れたのが、大量の問診表や同意書に目を通して、回答したりサインしたりする作業でした。もちろん全て英語なので、分からない言葉等をその場でグーグル翻訳しながら回答するので、かなり時間がかかりました。実際にどのような書類の内容だったのか紹介するので、知らないことや、英語での言い方が分からないものは、事前に調べて用意しておくと良いでしょう。
初診前に把握しておきたいこと
・保険会社と、かかりつけ薬局
・最終月経開始日
・妊娠前の体重(キログラム(kg) と ポンド(lb) 両方)
・家族の病歴(ガン、心臓病、高血圧、糖尿病、ダウン症、知的障害など)
記入した書類
・支払いに関する同意書(クレジットカード情報の提出あり)
・外科手術が必要になった場合の同意書
(急に外科手術が必要になった場合、その外科医が保険適用外の可能性があり、追加の支払いが発生する可能性があることへの同意書)
・HIV感染のテストを受けるかどうかの同意書
・問診表
※他にも書類を書いたかもしれませんが、記憶にあるのがこれだけでした
問診表の内容
覚えている限りの内容を紹介します。看護師さんとの問診でも同じようなことを聞かれるので、知らない英単語などは把握しておくと良いでしょう。
・名前、年齢、住所、電話番号、人種、最終学歴、婚姻状況など
・病歴(糖尿病、トラウマ、輸血歴など)
・婦人系病歴(乳がんなど、また不妊治療の有無など)
・タバコ、アルコールの頻度
・感染スクリーニング(B型肝炎予防接種歴、水疱瘡の歴など)
・遺伝子スクリーニング(35歳以上か、服用している薬はあるか、流産や死産の経験、家族に関してダウン症、知的障害、自閉症、心臓病、高血圧、ガンなど遺伝性疾患の有無など)
・過去の妊娠、出産歴
・現在の状況(吐き気、頭痛、便秘などの症状あるか)
・子宮頸がんの検査を最近したか
検診と質疑応答
アメリカの病院では、まず看護師さんとの問診があり、それをベースにドクターの診察を行うことが多いです。また、日本ではお医者さんと話している内に疑問や不安が解消されるということもあると思いますが、アメリカでは、こちらから質問しない限り、本当にあっさり診察が終わることも多いです。(ドクターにもよりますが。)なので、診察は受け身ではなく、積極的に自分から聞きたいことを聞く必要があります。聞き忘れがないように、事前に聞きたいことをまとめておくと良いでしょう。
質問の例
・つわりがひどくなったら、どうしたら良いか。飲んで良い薬は?
・日本に一時帰国したり、旅行に行く予定があるが、大丈夫か?
・どのような異常に注意するべきか、その時の連絡先は?
筆者がお世話になっていたドクターは、英語の苦手な日本人にも慣れていて、グーグル翻訳を駆使しながら分かりやすく説明してくれる方でした。また妊娠から出産までを全て解説したパンフレットと、よくある質問や緊急連絡先などがまとめられた冊子を貰うことができたので、ちょっとした困りごとや疑問はそれで解決することができました。書類で渡された情報(多くの人が気になるであろう項目)を以下にまとめたので、ドクターへ質問するときの参考にしてみてください。
知っておきたい情報抜粋(筆者が病院から紙でもらった情報)
・緊急連絡先、連絡方法
・飲んでも良い市販薬一覧
・摂取を控えるべきもの(カフェインとか)一覧
・妊娠中にしてはいけないこと一覧
・病院のマップ(駐車場、検診場所、出産場所)
服装
初診では、経腟エコーで胎児の様子を確認します。筆者の場合、下半身は全て衣服を脱ぐことになりますが、上半身は服を着たままだったので、ワンピース等よりは上下分かれた服装の方が良かったです。また靴は履いたままなので、脱ぎやすい靴の方が着替えやすいです。その後の定期健診では、下半身も脱ぐことなくお腹を出すだけで良かったので、やはり上下分かれた服が便利でした。ちなみに、体重測定もありますが、日本ほど厳しくないように思います。体重計に乗るとき「靴は脱いだ方がいいですか?」と聞いたら、どっちでも良いよと言われました。靴の重さは誤差です(笑)
また、病院は夏などクーラーが効きすぎていて寒い可能性があるので(アメリカあるある)、心配な方は上着があっても良いでしょう。
出生前診断について

初診で無事に胎児がいることを確認した後、ドクターと確認したのが、出生前遺伝子検査を受けるかどうかという話でした。そんな話が初診であると想定していなかった筆者は、ドクターの説明を理解するのに時間がかかりました。
赤ちゃんの遺伝子異常(genetic abnormarites)の可能性を把握するために、問診表で家族にダウン症などを持つ人がいるか聞かれます。そしてさらに、出生前遺伝子検査(出生前診断)の種類について説明がされ、その希望について聞かれました。アメリカでは、年齢に関係なく誰でも出生前遺伝子検査を受けることができ、保険適用の場合もあります。(カバー範囲は保険による。)アメリカ産婦人科学会(ACOG)は、すべての妊婦に、胎児の染色体の検査を受ることを推奨しているようですが、受けるかどうかは自己判断によります。胎児の遺伝子検査について、病院からもらったパンフレットの情報をもとに、簡単にまとめました。詳しい情報はかかりつけのドクターに確認してください。
胎児の遺伝子検査
出生前遺伝子検査(胎児の遺伝子検査:Prenatal genetic test)は、大きく2種類に分けられます。
・スクリーニング検査(Screening Test):赤ちゃんに遺伝性の病気がある"可能性(リスク)"を測定する
・診断検査(Diagnostic Test):赤ちゃんに特定の障害があるかどうか診断する
そして、検査カテゴリーが「染色体異常(chromosomal abnormalities)」、「キャリア障害(carrier disorders)」、「神経管欠損(neural tube defects)」の3つに分かれます。それぞれに色々な種類の検査があり、受ける時期は検査ごとに異なります。例えば、染色体異常で起こる症状のひとつであるダウン症は、約800人に1人の赤ちゃんに発生します。
NIPT
染色体異常のスクリーニング検査のひとつが「NIPT(Non Invasive Prenatal Testing:非侵襲性出生前遺伝学的検査)」(もしくはNIPS ; Non Invasive Prenatal Screeningとも呼ぶ)です。血液検査によって、胎児のDNAレベルを測定します。DNA検査なので、染色体異常だけでなく、希望すれば胎児の性別も分かります。ただしNIPTは偽陽性・偽陰性があるので、あくまで可能性を測定するだけで、病気を確定することはできません。早ければ妊娠10週から検査が出来ます。
第1期スクリーニング
「第1期スクリーニング(1st trimester screening)」では、血液検査と超音波検査の結果を組み合わせて遺伝子異常を判断します。どちらも妊娠10週~13週頃に行います。もしこれを行わない場合、初診の経腟エコーで胎児を確認した後、しばらくの間(20週頃の胎児の身体異常を確認するスクリーニングまで)、エコーで胎児を見る機会が無い場合もあります。
まとめ
アメリカで妊娠、出産を経験することになった場合、一番最初の難関が「産婦人科を探して初診を受ける」という人も多いと思います。たとえ通訳サービスを使える場合でも、聞きたいことは自分からしっかり聞く、というのが大きなポイントかもしれません。また日本とアメリカでは色々な違いがあります。初めて妊娠した人、日本では出産を経験したけどアメリカでは初めての人、少しでも不安を抱えている人の参考になればと思います。
*合わせて読みたいアメリカでの妊娠・出産に関する記事*
ブログランキングに参加してます。
気になった方、ポチポチしてもらえると嬉しいです!